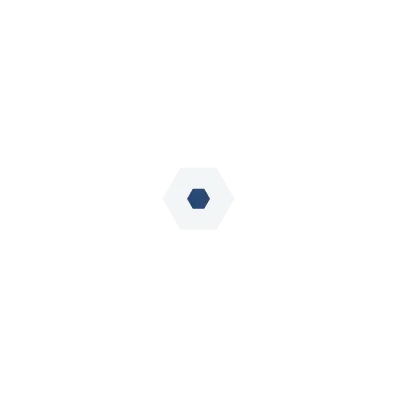高度なサービスを提供している事業所が取れる加算、特定事業所加算・日常生活継続支援加算とは?取るための要件は?詳しく解説します。
高度なサービスを提供している事業所が取れる加算、特定事業所加算・日常生活継続支援加算とは?取るための要件は?詳しく解説します。
近年、高齢化が進む我が国では、介護度の高い利用者の対応ができる介護事業所がますます求められています。そのため、国の方針として、介護度の高い利用者に対して質の高いサービスを行なっている事業所を評価する流れができてきているのです。
それを反映した加算として特定事業所加算や日常生活継続支援加算があります。
これらの加算を算定することで事業所経営にプラスになるとともに、今後の日本社会の中で必要とされる事業所を目指すことができます。
今回は特定事業所加算と日常生活継続支援加算の概要と算定要件について解説していきます。
特定事業所加算の概要と算定要件
要介護度の高い利用者や支援が困難な場合においても質の高い介護サービスを積極的に提供し、算定要件を満たす運用を実施している事業所に支払われる加算です。 特定事業所加算Iから特定事業所加算Vまであり、利用者の総単位数プラス5%―20%の加算を得ることができます。特定事業所加算I要件をみてみましょう
- 計画的な研修の実施
- 会議の定期的開催
- 文書等による指示及びサービス提供後の報告
- 定期健康診断の実施
- 緊急時における対応方法の明示
- ⑦人材要件
- 重症者要件
日常生活支援加算の概要とその要件
居宅での生活が困難な重度要介護者や認知症などで施設入所の必要性が高い利用者を施設が積極的に受け入れる様にすることを目的とした加算です。 日常生活支援加算Ⅰの場合、1日当たり36単位、日常生活継続支援加算Ⅱの場合、1日当たり46単位取得できます。要件としては以下のものがあります
- 新規入所者のうち 要介護4・5の認定を受けている人が70%以上
- 新規入所者のうち認知症日常生活自立度III以上の入所者が65%以上
- 医師の指示に基づいた喀痰の吸引や経管栄養を行う必要がある利用者が15%以上
- 介護福祉士が常勤換算で利用者6人に対して1人以上であること
- 通所介護等の算定方法第12号の基準に該当しない