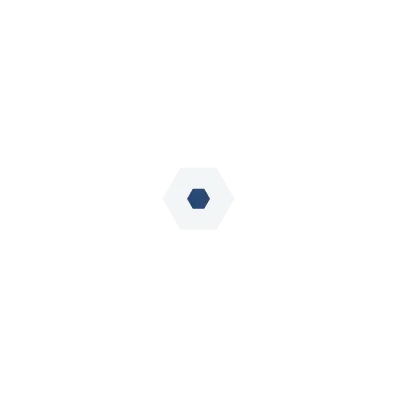施設が喀痰吸引のできる職員を確保するメリットとは?喀痰吸引で算定できる加算について解説します。
近年ますます我が国の高齢化が進む中で、施設利用者さんで喀痰の吸引が必要になる方がどんどん増えてきています。
しかし、常に安定して喀痰吸引ができるという事業所は全体の1割にも満たず、まだまだ喀痰吸引を実施できる事業所が足りていないという状況にあります。
利用者が肺炎などを起こして病院に入院し、退院する際に喀痰吸引が必要になった場合に元にいた施設に帰ることができず、利用者本人や家族に負担がかかったり、病院からの退院が遅れてしまうことも非常に多くなっています。その様な状況から喀痰吸引のできる事業所を増やすことが国の方針となっており、喀痰吸引を行うことで様々な加算が取れる様になっています。
喀痰吸引を行うことで利用者の増加に加えて、様々な加算の算定が可能になるので、事業所が喀痰吸引のできる職員を確保することのメリットは大きくなっています。
介護保険で取れる加算
介護保険での加算は、喀痰吸引を実施すれば直ちに取れるというものではないのですが、喀痰吸引を行うことが算定要件として取れる加算があります。
喀痰吸引を必要とする状態の利用者でも受け入れることができ、適切なサービスを提供できることが評価されるのが特徴です。
どの様なものか見てみましょう。
特定事業所加算
専門性の高い人材が揃っており、介護度が高い利用者に対しても十分なサービスが提供できる事業所を評価する加算です。
この加算を算定するためには国が定める要件を満たす必要があり、条件を満たした上で届出を行えば所定の単位数に5%−20%加算されます。
この加算を取るための要件の中に「利用者の総数のうち、要介護4及び要介護5であるもの、認知症日常生活自立度ランクIII、IV、またはMである者並びに痰の吸引等が必要なものが占める割合が20%以上である」
この要件を満たすためには職員の中に喀痰吸引ができる人が多くいる必要があり、喀痰吸引のできる職員の存在が非常に重要な要件となっています。
日常生活継続支援加算
居宅での生活が困難になっている重度の要介護者や認知症患者の方で、入所の必要度が高い利用者の積極的な受け入れを促進することを目的とした加算です。
この加算の算定のためにも喀痰吸引についての要件があり、「医師の指示に基づいた喀痰の吸引や経管栄養を行う必要がある利用者が15%以上であること」となっています。この要件を満たそうとすると当然、喀痰吸引のできる職員が常時勤務していることが求められます。喀痰吸引等研修を受けて、喀痰吸引ができる介護職員の存在は非常に重要と言えるでしょう。
障害者総合支援法で算定できる主な加算
障害者総合支援法で算定できる加算をみていきましょう。
喀痰吸引等支援体制加算
喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が医療機関との連携により喀痰吸引等を行なった場合に1日につき所定単位数を加算することができます。
医療連携体制加算
こちらも喀痰吸引等支援体制加算と同様に、喀痰吸引が必要な者に対して登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が医療機関との連携により喀痰吸引等を行うことで算定できる加算です。
ここで注意したいのが「登録特定行為事業者」と「認定特定行為業務従事者」という言葉です。喀痰吸引を実施するためには、まず事業所が登録特定行為事業者として登録をしている必要があります。登録を済ませていないと、加算が取れないばかりか、喀痰吸引のできる資格を持っている介護職員であってもその事業所での喀痰吸引ができないのです。
喀痰吸引等研修を受けても登録されている事業所でないと喀痰吸引はできません。
また喀痰吸引ができないと、緊急事態に対応できない、高齢化社会における利用者のニーズに応えにくいなどのデメリットもあります。今後の今後ますます高齢化社会となった際に喀痰吸引ができる職員が揃っていることは施設に対して大きなプラスになると思われます。
まとめ
今回は喀痰吸引のできる職員をしっかりと揃えることで算定できる加算について解説していきました。喀痰吸引を実施すること自体で算定できる加算があり、また喀痰吸引をすることが算定の要件となっているか加算も多くあります。
また今後高齢者がますます増えていくと、昼夜問わず喀痰吸引を必要とする人の数は多くなることが予想されます。喀痰吸引のニーズが今後拡大していく中で、それに対応できる職員が多くいる施設に有利な制度や加算が新たに増えていく可能性も高いのです。
喀痰吸引のできる職員を増やしていくことは施設の経営にプラスになり、社会的なニーズを満たすことのできる事業所づくりにもなるので、喀痰吸引のできる職員の育成はどの事業所にとっても重要であると言えます。