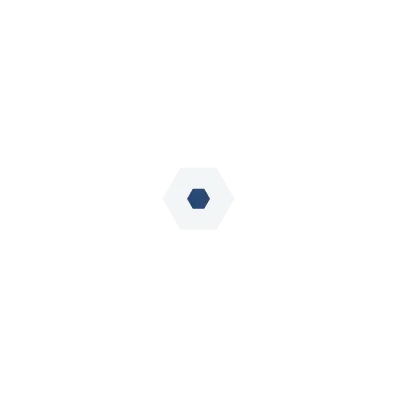介護保険総合データベースとは?
目次 [閉じる]
要約:
介護保険総合データベースは、厚生労働省が介護保険法に基づき、要介護認定情報、介護レセプト情報、LIFE情報を匿名化して収集したデータベースです。このデータは、介護保険事業計画の策定や介護サービスの質向上、日本国民の健康維持を目的として利用されています。利用には厳格なガイドラインが定められ、申請者の資格や利用目的が審査されます。データは公的機関や研究機関に限定提供され、適切な利用と安全管理が求められます。株式会社プレゼンス・メディカルでは、このデータを活用したAIソリューションを提供し、介護業界の課題解決やオープンイノベーションを推進しています。この取り組みは利用者と従業員のQOL向上を目指しています。
自分の所属する研究機関では介護に関する研究を行っているけれど、信頼のおけるデータを収集するにはどうすればよいか悩ましく感じている人はいませんか?
この記事ではそんな人に知ってほしい、介護保険総合データベースについて詳しく解説します。

介護保険総合データベースとは?
介護保険総合データベースとは、厚生労働省が介護保険法に基づき以下の情報を個人が特定できない形で集め、匿名化したデータベースのことです。
- 要介護認定情報
- 介護レセプトなどの情報
- LIFE情報
介護保険総合データベースに集められる情報は、どれも個人情報として取り扱いに注意しなければならない内容ばかりなので、匿名化されているとわかります。
4つの情報が具体的にどのようなものなのか解説します。
要介護認定情報
要介護認定情報とは市区町村が要介護認定に用いた調査の結果で、2009年4月~2024年1月までに収集された約8,300万件のデータを指します。
格納されている主なデータは以下の通りです。
|
項目 |
概要 |
|
要介護認定一次判定 |
l 基本調査74項目 l 主治医意見書のうち、短期記憶、認知能力、伝達能力、食事行為、認知症高齢者の日常生活自立度の項目 l 要介護認定等基準時間 l 一次判定結果 |
|
要介護認定二次判定 |
l 認定有効期間 l 二次判定結果 |
個人が要介護認定を受ける際に必要な、生活における能力の現状が詳細に記されたデータとそれに基づいてどのような要介護度と判断されるのかがわかる資料です。
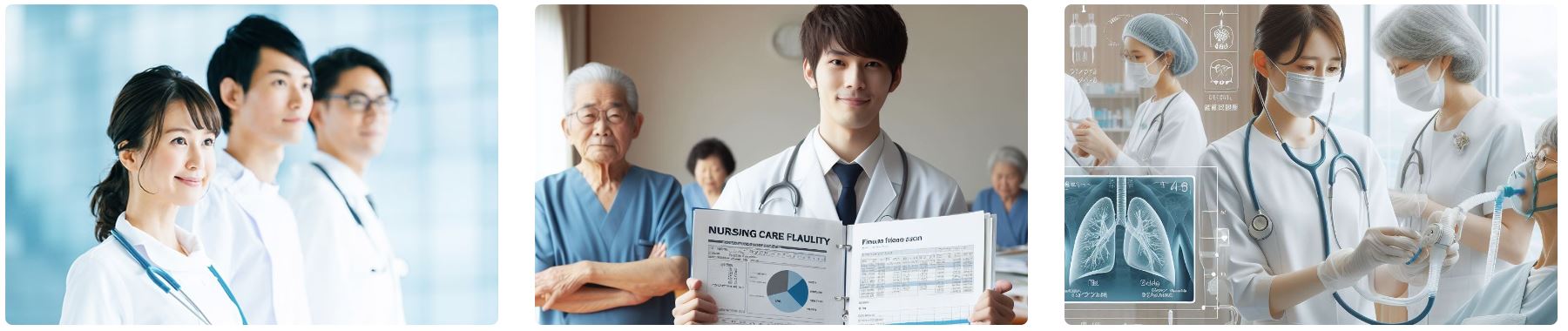
介護レセプトなどの情報
介護レセプトなどの情報とは、審査支払機関となっている国民健康保険団体連合会を通じて保険者に請求される介護レセプトに記載されている内容で、2012年4月~2024年1月までに収集された約19.9億件のデータを指します。
格納されている主なデータは次の通りです。
|
項目 |
概要 |
|
属性 |
l 性別 l 生年月日 l 要介護状態区分 l 認定有効期間 l 保険分給付率 |
|
サービス内容 |
l サービスの種類 l 単位数 l 日数 l 回数 |
個人がどのような介護サービスをどのくらい受け、どの程度の介護給付を受けたのかがわかるデータです。
LIFE情報
LIFE情報とは、介護サービス事業者がLIFE(科学的介護情報システム)に入力した利用者の状態像やケアの内容に関する情報で、2021年4月~2024年1月までに登録した約2.6億件のデータを指します。
格納されている主なデータは以下の通りです。
- 利用者の情報
- ケアの内容の情報
- 科学的介護の推進情報
介護サービスを受けた個人の状態を記録・分析・評価してあるため、将来に向けて介護の質を向上させるために役立つデータです。
参考:厚生労働省「匿名介護保険等関連情報データベース (介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン第3版」
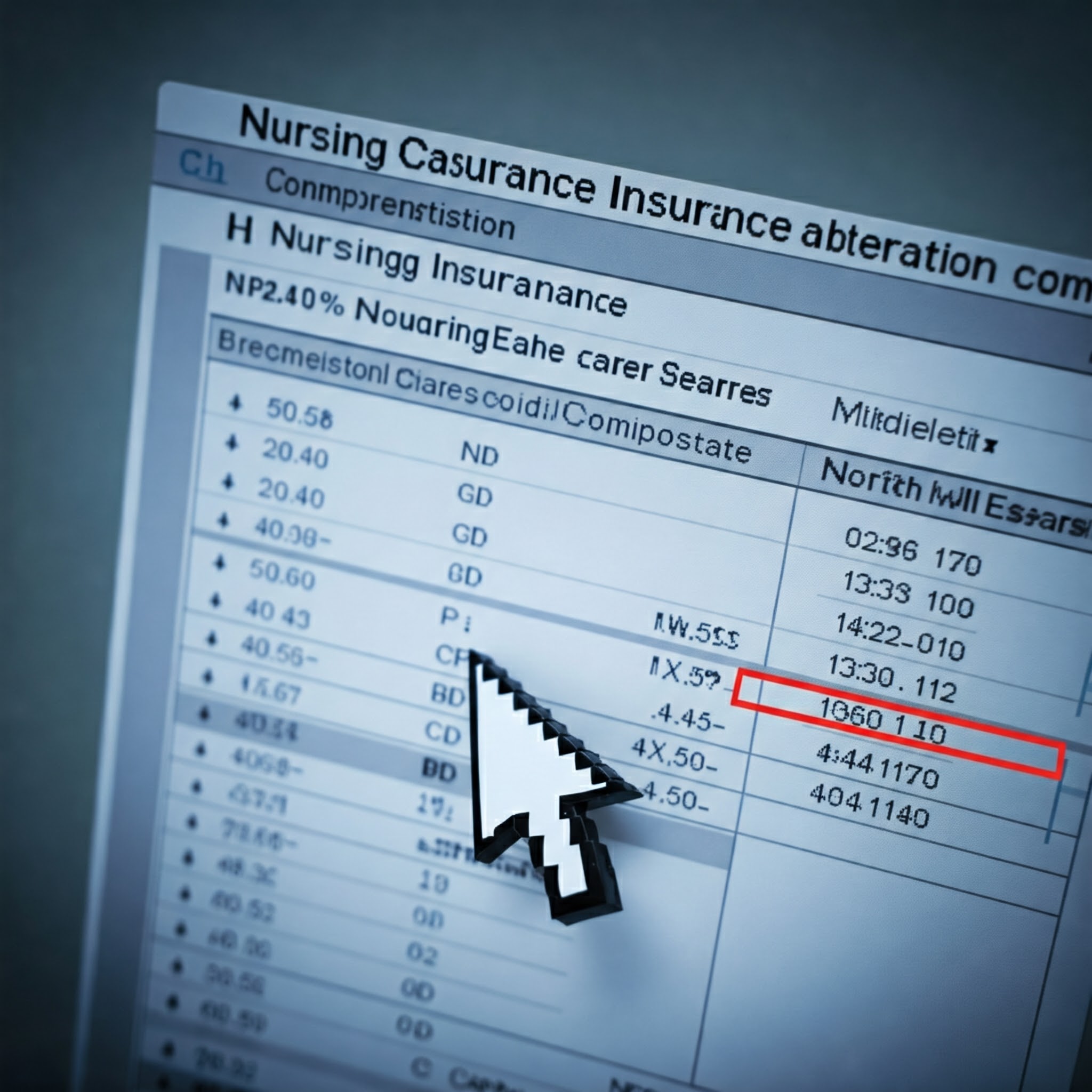
介護保険総合データベースの情報を収集する目的
介護保険総合データベースの情報は、以下の目的で集められています。
- 介護保険事業計画などの作成や実施
- 日本国民の健康の保持増進
- 日本国民の持つ能力の維持向上
介護保険サービスを今後どのような形で続けていくかを検討したり、被保険者が健康に生活するためにはどうしたらよいかを考えたりするのを目的として情報収集が行われていると言えるでしょう。
介護保険総合データベースの現状
厚生労働省の社会保障審議会に2020年10月1日から「介護保険部会匿名情報等の提供に関する専門委員会」が新設され、現在も継続的に介護保険総合データベースについての話し合いが行われています。
直近では2024年12月9日にも介護保険部会匿名情報等の提供に関する専門委員会が開催され、定型データセット(提供申出によらない一定の条件で全項目を抽出したデータセット)開始後のデータ提供や不適切利用などについて検討が行われました。
介護保険部会匿名情報等の提供に関する専門委員会での話し合いは今後も続けられる予定となっているため、その内容に応じて介護保険総合データベースの内容や運用方法がよりよいものに変化していくでしょう。
参考:厚生労働省「社会保障審議会(介護保険部会匿名介護情報等の提供に関する専門委員会)」

介護保険総合データベースの利用方法
介護保険総合データベースはどのようにして利用すればよいのでしょうか。
介護DBオープンデータ、介護保険総合データベースを利用できる人、介護保険総合データベースの利用の流れの3つの観点からご紹介します。
介護DBオープンデータ
厚生労働省のホームページでは、介護保険総合データベースのデータから汎用性の高い基礎的な集計表を作成し、「介護DBオープンデータ」として公表しています。
2024年12月現在、2018年度~2019年度までの要介護認定情報を集計した第一回介護DBオープンデータ、2020年度~2021年度までの要介護認定情報、LIFE情報、介護レセプト情報を集計した第二回介護DBオープンデータが公開されているのです。
介護保険総合データベースの概要を知っただけでは具体的にどのようなものかイメージできない人は、まず介護DBオープンデータに目を通してみることをおすすめします。
介護保険総合データベースを利用できる人
介護保険総合データベースを利用できる人の範囲は、「匿名介護保険関連情報データベースの利用に関するガイドライン第3版」で以下のように定められています。
|
項目 |
概要 |
|
公的機関 |
l 国の行政機関 l 都道府県 l 市区町村 |
|
法人など |
l 大学 l 研究開発行政法人など l 民間事業者 |
|
個人 |
l 補助金などを用いて業務を行う個人 |
前の項目でもご紹介した通り、介護保険総合データベースには匿名の個人情報であっても取り扱いに特に注意しなければならない情報が多数含まれるため、すべての人が利用できるわけではありません。
目的もなく興味本位で見られる情報ではないということを覚えておきましょう。
参考:厚生労働省「匿名介護保険等関連情報データベース (介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン第3版」
介護保険総合データべースの利用の流れ
介護保険総合データベースの利用の流れは以下の通りです。

提供申出書の作成
介護保険総合データベースの利用を希望する個人や機関(提供申出者)は、厚生労働省が定めた様式に従って次の9つの事項を提供申出書に記載しなければなりません。
|
項目 |
概要 |
|
ガイドラインなどの了承の有無 |
l 提供申出者と取扱者(提供申出書に記載された実際にデータを取り扱う人)が厚生労働省「匿名介護保険等関連情報データベース (介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン第3版」の内容を了承していることを記載する l 提供申出者が介護保険総合データベースを利用した研究をするのを承認している書類を添付する |
|
担当者と代理人 |
l それぞれの氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名、部署名、職名、電話番号、E-mailアドレスを記載する l ガイドラインで指定された本人確認書類を添付する |
|
提供申出者の情報 |
l (公的機関の場合)名称、担当する部局、所在地、電話番号を記載する l 所属する取扱者1名以上について身分証明書とその機関に所属していることを証明する書類を提出する l (法人の場合)名称、所在地、法人番号、法人等の代表者か管理人の氏名、職名、電話番号を記載する l (個人の場合)、氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名、部署名、職名、電話番号、E-mailアドレスを記載する l 提供申出者の本人確認書類を提出する |
|
研究計画 |
次の9項目を記載する ① 研究の名称 ② 研究の内容と必要性 ③ 研究の概要 ④ 研究の計画と実施期間 ⑤ 他の介護・医療データとの連結の有無 ⑥ 外部委託について ⑦ 取扱者の過去の実績と現在行っている研究 ⑧ データを利用する期間(上限は24か月間) ⑨ データの利用場所と保管場所 |
|
取扱者 |
l 全員の氏名、所属機関名、職名、電話番号、E-mailアドレス、利用場所を記入する |
|
抽出データ |
l 希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等などを記入する |
|
成果の公表予定 |
l 予定するすべての公表方法、公表先、公表の内容、公表予定時期を記入する |
|
提供方法、手数料免除、過去の利用実績 |
l データの提供方法、手数料免除の申請について、過去に介護保険総合データベースを利用したかどうかを記入する |
|
その他必要な事項 |
l 厚生労働省が必要に応じて求める事項 |
提供申出書と一緒に以下の書類も提出が必要です。
- 介護保険総合データベースのデータの管理方法と安全管理対策に関する書類
- 倫理審査にかかる書類
これらの書類を作成したら、厚生労働省老健局老人保健課にメールで送付しましょう。
書類に不備があれば修正や再提出で時間がかかるので、ホームページをよく確認の上、定められた期限までに提出するようにしてください。

審査
介護保険総合データベースのデータを提供するかどうかは介護保険法に基づいて専門委員会が審査をした上で判断します。
審査基準の項目は次の通りです。
- 提供申出者、担当者、代理人の氏名など
- 介護保険総合データベースのデータの利用目的
- 提供を希望するデータの概要と介護保険総合データベースの利用の必要性
- 研究体制など
- 安全管理対策
- 定型データセットを利用する場合の管理方法
- 結果の公表予定
- その他の必要事項
審査基準の詳細は厚生労働省「匿名介護保険等関連情報データベース (介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン第3版」に書いてあるため、審査を通過できるかどうか不安な人は内容を確認しておきましょう。
厚生労働省は専門委員会による審査の結果を踏まえて、データ提供の可否を承諾通知書または不承諾通知書で通知します。
依頼書と誓約書の提出
審査の結果承諾通知書が届いた場合、必要な事項を記載した依頼書でデータ提供を依頼しなければなりません。
また提供申出者、取扱者全員が利用規約を確認して順守することを記載し署名した誓約書の提出も必要です。

手数料の納付
介護保険総合データベースのデータ提供を受ける場合、介護保険法施工令第37条の17に記載された提供に必要な時間1時間につき5,900円という単価に、作業にかかった時間をかけて求めた手数料がかかります。
作業にかかった時間とは、以下の2つの業務をするためにかかった時間のことです。
- 申出処理業務
- データ抽出業務
例えば申出処理業務に2時間、データ抽出業務に3時間かかったとすると、合計5時間なので5,900円×5時間=29,500円を手数料として支払わなければなりません。
厚生労働省が手数料の実績額と納付期限を通知するので、厚生労働省が定める書類に収入印紙を貼って納付しましょう。
データの受領
介護保険総合データベースのデータ提供を受けたら、厚生労働省宛にメールで受領書を送付する必要があります。
もしデータを分割で受領したり、変更申出をして再度データを受領したりした場合も都度送付しなければならないので注意しましょう。
研究成果の公表
介護保険総合データベースのデータ提供を受けて研究をしたら、その成果を提供申出書に記載した公表時期、方法に基づいて公表します。
公表物が満たさなければならない基準は厚生労働省「匿名介護保険等関連情報データベース (介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン第3版」に詳細が記載してあるため事前に確認しましょう。
また公的機関以外の利用者は研究成果の公表後3か月以内に、成果の概要について厚生労働省に「利用実績報告書」で報告を行わなければなりません。
もし介護保険総合データベースを利用している過程で、当初予定していた研究の成果が挙げられないとわかった場合、データを速やかに返却し、消去する必要があるのも覚えておきましょう。
厚生労働省は報告を受けた利用実績を取りまとめて専門委員会に報告し、必要に応じて利用実績をホームページなどで公表します。
参考:厚生労働省「匿名介護保険等関連情報データベース (介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン第3版」

介護保険総合データベースの不適切利用への対応
介護保険総合データベースを利用する人には介護保険法に基づき次のような義務が課せられています。
- 他の情報とデータを照合する行為の禁止
- 利用後はデータを消去する
- 安全管理措置を取る
- 不当な目的で利用する行為の禁止
法令違反の疑いがある利用者に対して、厚生労働省は介護保険法に基づく立ち入り検査、是正命令を行うことができます。
また上記の義務や是正命令に違反した利用者には、介護保険法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50万以下の罰金)が科される場合があるので注意しましょう。
参考: 厚生労働省「匿名介護保険等関連情報データベース (介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン第3版」
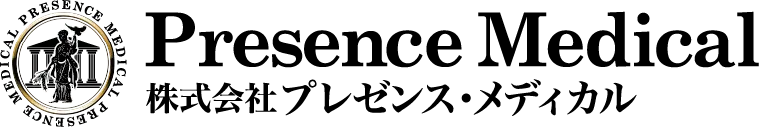
オープンイノベーションの考え方を大切にしています
株式会社プレゼンス・メディカルでは「未来の介護を創る、オープンイノベーション」をテーマに介護×テクノロジーで介護業界における課題を解決しています。
具体的には課題解決をする上でデータ活用を重要視し、利用者の日常生活に関するさまざまなデータをAIが分析することで見守り強化や健康管理を支援しているのです。
弊社が提供しているAIソリューションは以下の通りです。
(利用者向け)AIを活用した介護施設の医療連携サービス
(利用者向け)認知症予防・自立支援・健康管理を実現するAIサービス
(利用者向け)AIを活用したコミュニケーション支援サービス
(利用者向け)AIを活用した介護施設のロボット活用・見守り・セキュリティサービス
(従業員向け)AIを活用した訪問介護・看護の効率化サービス・シフト管理・配車手配
(従業員向け)AIを活用した介護施設の業務効率化・生産性向上サービス
(従業員向け)AIを活用した介護施設の採用支援・働き方改革支援サービス
(従業員向け)AIを活用した介護施設の離職防止と教育サービス
介護保険総合データベースを活用する大学や地方自治体が増えれば、介護に関する研究が今よりさらに進み、弊社とのオープンイノベーションの機会も増えると考えています。
オープンイノベーションの機会が増えれば上記のAIソリューションの内容もさらに充実させることができるため、介護施設において利用者と従業員双方のQOL(生活の質)を高められるでしょう。
弊社のAIソリューションに興味をお持ちの方は、次のページもごらんください。
FUNCTIONS&PRODUCT | 喀痰吸引等研修の講習・資格・介護・福祉の研修実績|株式会社プレゼンス・メディカル
まとめ
介護保険総合データベースは、厚生労働省が介護保険法に基づいて匿名化された要介護認定情報、介護レセプト情報、LIFE情報を収集したデータベースです。これらの情報は、介護保険事業計画の策定や介護サービスの改善、日本国民の健康維持を目的に活用されます。データの利用には申請手続きや専門委員会の審査が必要で、公的機関や大学、研究開発法人などに限定されます。また、適切な安全管理と利用目的の遵守が義務付けられており、違反時には法的措置が取られることもあります。株式会社プレゼンス・メディカルは、介護保険総合データベースの情報を基にAIソリューションを提供し、介護施設における課題解決や効率化を実現。利用者と従業員双方の生活の質(QOL)向上を目指し、介護業界全体の進化を促進しています。本記事を参考に、介護保険総合データベースの利用価値をさらに深く理解してみてください。
本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。