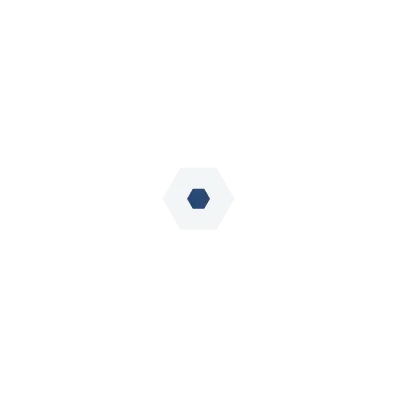2020年6月1日に「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正法が施行されました。この法律は通称「パワハラ防止法」と呼ばれていて、近年問題になることの多いパワーハラスメントを予防するために施行されています。
医療機関においてもパワーハラスメントは問題となりやすく、知らず知らずのうちに職場でパワハラが蔓延しているということもあります。パワハラ対策を講じないことで職場環境の悪化、重大な医療事故の発生、職員の離職など大きな問題が出現する可能性があり、「しらなかった」では済まされない問題となります。
今回はパワハラについて解説し、パワハラ防止法とはどのような法律なのかを見ていきます。
パワーハラスメントとは?
パワハラとは以下の3つの要件を満たすものを言います。
・優越的な関係が背景にある。
・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がある。
・就業環境を害する。
大まかにまとめると「業務上逆らえない人から、業務に支障をきたすような。適切な指導の範囲を超えた指導や言動をうける」ということになります。
パワハラ防止法について
パワハラ防止法では以下の措置が義務付けられています。
- 事業主の方針の明確化と周知
- 相談窓口の設定と相談の対応
- パワハラに関わる適切な対応
- 合わせて講ずべき措置
まず事業主はパワーハラスメントに対してどのように対応するのかをしっかりと周知する必要があります。研修を行なったり冊子などを配布するなどして十分に行います。
相談窓口を設けて、相談する人が来た場合には、事実の正確な確認を行い速やかにそれに対する措置と再発予防を目に見える形で行う必要があります。合わせて構ずるべき措置としてプライバシー保護、秘密保持、不当な扱いの防止といったものがあります。
これらの義務を守らないことに対して特に罰則があるというわけではありませんが、パワハラが発生して明るみに出たさいにこれらの義務を守っていなかった場合には相当の社会的責任を負わされることとなったり、パワハラが常態化して改善が見られない企業は企業名が公表されたりといった措置があります。
病院でのパワーハラスメントの実情
病院でのパワハラの実情はどのようになっているのでしょうか。見ていきましょう。
じつは病院はパワハラが起きやすい環境となっています。
病院での仕事は以下のような特徴があります。
・ミスが許されず緊迫した状況になりやすい
・対人関係でのストレスが発生しやすい
・忙しく 急に対応しなければならないことも多くマネジメントが難しい
このような環境の中で仕事をしていると故意に嫌がらせをしようとしていなくても、上司からの指導がつい厳しくなってしまったり、対人関係のストレスが知らず知らずのうちに部下に向かってしまったりしやすいのです。
また専門家の集団でありここの職員が自律的に動いているというのがパワハラに気付きにくくなります。
このような環境なのでパワハラの発生には注意を払うことが重要になります。
パワハラには以下のような種類があります。
具体的な事案例とともに見ていきましょう
・身体的な攻撃
仕事ができない人をこづく 長時間廊下に立たせるなどの懲罰
・精神的な攻撃
カンファレンスなどで大声で怒鳴り続ける ミスを大声で叱責する
・人間関係からの切り離し
カンファレンスなどに参加させない 「説明しても分からないだろう」などといって必要な説明をしない
・過大な要求
1日では到底終わらないような診療業務を押し付ける 担当患者数が多すぎる
・過小な要求
医療業務をさせず電話番や受付だけをやらせる
・個の侵害
彼氏の有無をしつこく聞く 連絡先をしつこく聞く
上記のようなことはじつは日々病院内で発生しているのですが問題にされないことも多く早期に発見して是正することが求められます。
パワハラ対策はまず相談しやすい環境から
パワハラは程度の軽いうちに対応できれば大きな問題となることなく、少しの指導で改善できる場合が多くあります。パワハラをする側も故意の嫌がらせをしている例よりは指導をしなければいけないという気持ちから表現が強くなってしまう場合が多いためパワハラを自覚しておらず指導されることで改善することも多いためです。
つまりパワハラを相談しやすい環境がパワハラの問題を大きくすること防ぐのに有効です。事業所内の窓口を充実させるのも重要ですが、事業所内の人間に知られずに相談できる外部の窓口を利用し、それを積極的に周知するのも有効なパワハラ対策になります。
普段から風通しの良い職場にすることがパワハラ対策では何よりも重要と言えるでしょう。
まとめ
今回はパワハラ防止法について解説しました。
パワハラは程度の軽いものであれば実は日常席に発生しています。
「このぐらいなら大丈夫だろう」と思ってやっていることでも受けた側が「パワハラだ」と感じていれば大きな問題となることがあります。パワハラの発生状況を共有できる風通しの良い職場になることが最も有効な対策となります。